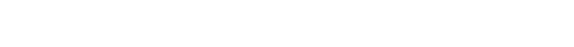
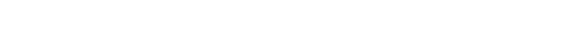
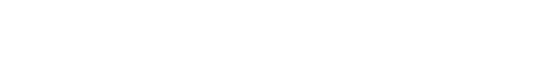

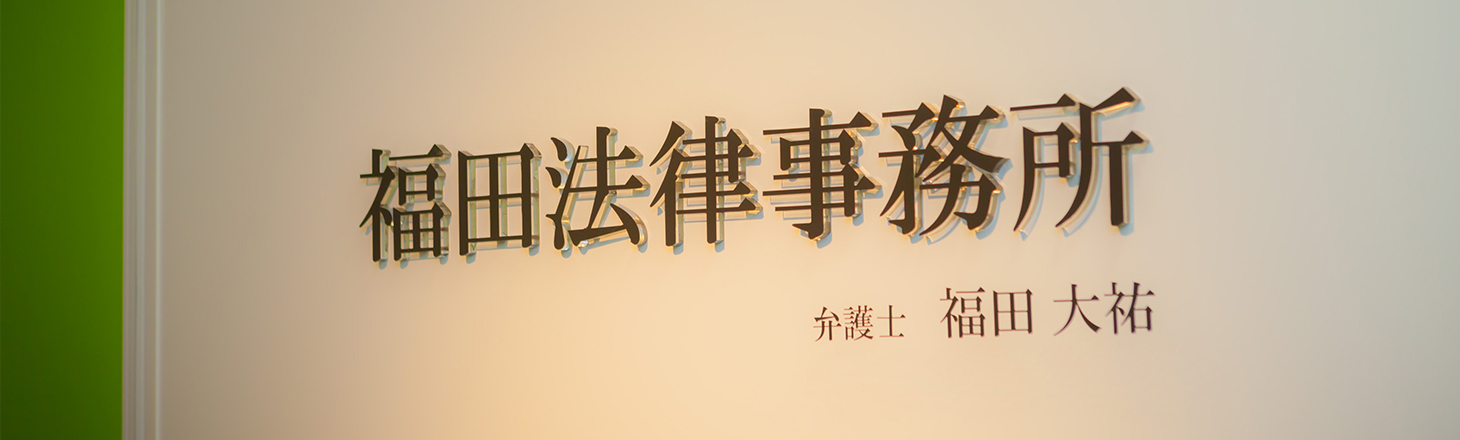
相続が生じたとき、なんの疑問もなくトラブルもなくスムーズに遺産分割がまとまり、税金の支払いや登記名義の変更まで完了することは実は少ないかもしれません。
相続についての疑問やトラブルについては誰に相談すればよいのでしょうか?
相続問題を相談できる専門家にはどのような種類があるのでしょう。詳しく見ていきましょう。
弁護士は相続をめぐるすべての法律問題について対応可能な専門家です。
相続は、相続人は誰なのか、相続財産はどれだけあるのか、遺言書は有効なのか、等々根本的なところから法的な解釈や知識が必要となります。
また、弁護士は交渉や調停など普段から依頼者の代理人として相手方と折衝する業務に従事しており、相続人間のトラブルについても、相手方と法律的な知識をもとに交渉したり、交渉がまとまらなかったときには訴訟の代理人となったりします。 これは、弁護士しかできない業務です。
相続人の間で遺産分割をめぐる争いが生じれば、弁護士に相談するべきでしょう。
また、相続開始前に、弁護士と一緒に遺言の内容を整理し、遺言書を作成して、弁護士を遺言執行者に指定しておくこともできます。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現させるために、相続登記や預貯金の管理など必要な手続を行う立場の人です。遺言執行者は各相続人の代表として、被相続人の死後の遺産分割において、相続財産を管理します。
また、被相続人が、相続開始前に認知症などになったときも、その時点で弁護士に相談すれば、成年後見制度の利用など、必要かつ適切なアドバイスをしてくれるでしょう。
司法書士は140万円以下の簡易な事案なら弁護士と同じように法律代理業務ができます。
また、相続財産の中に不動産がある場合、登記名義を相続人に変更しなくてはなりません。
この「不動産登記手続き(名義変更)」については、司法書士が専門家です。
相続にともなう登記名義の変更には相続人調査として、戸籍の取り寄せが必要となりますが、これも司法書士であれば業務として行うことができます。
実は、弁護士も登記手続はできるのですが、登記手続は司法書士に任せている弁護士が多く、結局は登記に関しては司法書士の方が専門性が高いといえるでしょう。
登記名義は、相続開始後も、亡くなった人の名義のまま放置している人も少なくありません。
しかし、死亡後いつまでも亡くなった人の名義のままではいろいろな不都合が生じます。
不動産を処分するときに再度遺産分割協議をする必要があったり、不動産の権利者が誰なのかが不明確なまま放置されたりと、トラブルの原因となります。
また、そのまま長期間が経過すると、相続人の誰かが死亡することもあるでしょう。その場合,さらにその妻・子供が相続人になるため登記手続が複雑化します。
相続後は、できるだけ早く相続登記を行いましょう。
行政書士は書類作成ができる専門家です。
相続に関するものとしては「遺言書の作成」、「遺産分割協議書作成」などが可能です。
また、相続人調査も可能です。
もっとも、行政書士は基本的に書類作成とそれに関連した法律アドバイスなどは認められていますが、その範囲を超えた遺産相続全体についてのアドバイスなどは難しいかもしれません。
税理士は税金に関する専門家です。税理士な税務署への申告手続を得意とします。
相続についての申告といえば、相続税の申告です。
被相続人から相続した預貯金・株式等を算定して、基礎控除額(3000万円+相続人の人数×600万円)を超えた分については、相続税の対象となります。不動産については、特例があり優遇を受けられる場合があるので、税理士に相談すれば特例の適用に関するアドバイスも受けられます。
ですので、多額の遺産を相続した場合やこれから相続する可能性がある場合には税理士に相談すべきでしょう。
相続税には特例などもありますので、税金を払わなくてよい場合に該当するかもしれませんので、この点もアドバイスしてもらえると安心です。
弁護士も、税理士登録をすることは可能ですが、やはり税金関係が専門の税理士さんに税金関係は任せていることが多いです。
相談に関する相談について、各専門家のできることや、おおまかな役割分担はご理解いただけたでしょうか。
弁護士は、割高なイメージがあるかもしれませんが、他の専門家のところで、結局扱えないことが発覚して、費用を二重に払うことを考えると、弁護士に多くの弁護士事務所は、司法書士や税理士とも提携していますので、まず相談してみるのも一つの選択肢だと思われます。