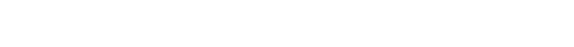
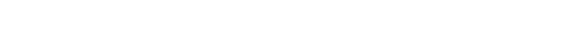
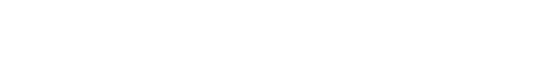

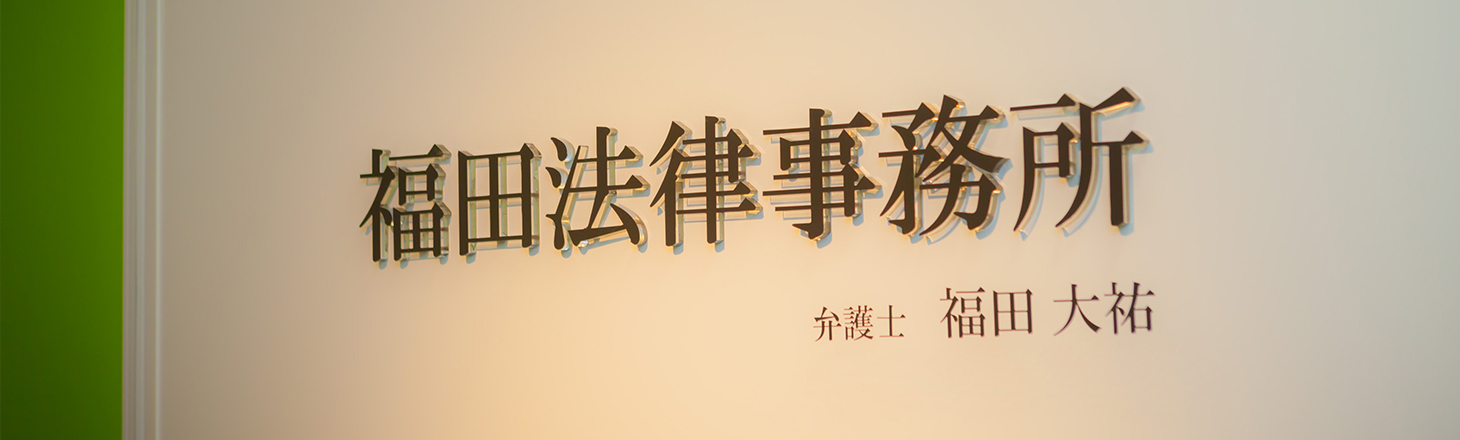
相続により株式を相続する人は意外と多いかもしれません。
被相続人が小さな株式会社を経営している場合もあるでしょうし、上場会社の株式を優待目的で保持していた場合もあるでしょう。あるいは勤め先で持ち株があった場合もあるかもしれません。
株式と一口にいっても、どのような会社のどのような株式かで相続する際の手続きも異なります。
株式を相続する場合にどのような点に注意をすればいいのかをみていきましょう。
まず、相続財産となる株式がどこにどの程度あるのかを調査します。
それも株式の種類によって調査する方法は異なります。
証券取引所で売買されている株式を上場株式といいます。
上場株式は、証券会社や信託銀行、その他の銀行などの金融商品取引業者等が管理をしています。
よって、被相続人が上場株式を保有していたか、どの銘柄の株式会社がどの程度あるかについては、窓口となっている証券会社や信託銀行等に確認すれば分かります。窓口となっている会社から定期的に書類が送付されていることが多いので、その書類を確認して会社へ取引残高報告書の発行を依頼することでれば明らかになります。
中小企業を経営していたり、中小企業を経営している友人に頼まれて出資している場合には、非上場株式を保有していることがあります。
このような株式は、先の上場株式と反対に、証券会社等が管理しているわけではないので、株式を発行している会社に直接問い合わせることになります。
なお、非上場株式会社の発行する株式は、譲渡制限付株式であることが多々あります。しかし、譲渡制限付株式であっても、相続人は相続を理由とする場合には、会社の承認なしに株式を引き継ぐことができます。
もっとも、会社法では、一定の場合に、株式会社が相続人に対して譲渡制限株式を会社に売り渡すように請求する権利がある旨規定しています。会社から株式の売渡請求を受けた場合、譲渡制限付株式の相続人は、株式の対価を取得することになります。
株式は、相続と同時に当然分割されて、各相続人のものとなるものではありません。
たとえば1000株を有していて、3人相続人がいた場合には端数がでますし、株式は、議決権を行使したりする株主の権利でもあるからです。
ですから、被相続人が持っていた株式は、相続によって相続人全員の「共有」となるのです。
つまり、相続人が遺産分割協議をして、相続人全員の合意のもと、相続すると決まった人が株式を被相続人から引き継ぐことになるのです。
株式を相続した相続人は、会社に株式の名義書換をしてもらうことになります。
この手続きは、通常、会社が株主名簿の管理を任せている株主名簿管理人(通常は信託銀行や証券代行会社)の窓口ですることになります。
株券が発行されている場合は株券を持って窓口に行くことが必要です。
発行されているはずの株券が見当たらないときは、株券発行会社に対して、株券を喪失した旨を「株券喪失登録簿」に記載または記録することを請求します。
その記載または記録から1年すれば、株券が無効となりますので、その後に名義書換の請求をすることができるようになります。
株式を相続することについてご理解いただけたでしょうか。
株式はそもそもその存在の調査が必要ですし、株式には、さまざまな種類のものがあることがあり、相続人にとってはまったくわけがわからないことも少なくないかもしれません。
また被相続人が会社経営をしており、株式とともに会社の事業を引き継ぐこともあるでしょう。
いずれにしても、株式の相続について少しでもわからないことがあれば、弁護士に相談することが大切です。