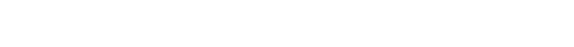
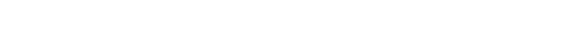
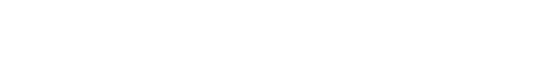

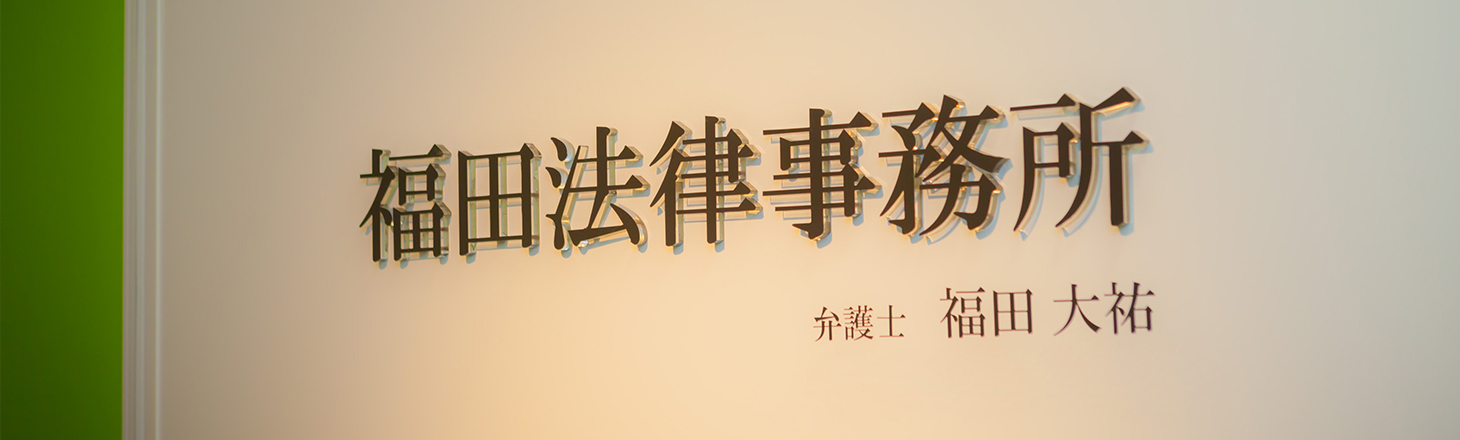
複数の相続人がいると遺産分割協議が必要です。協議がうまくまとまれば良いのですが、揉め事やトラブルに発展することも珍しくありません。揉め事やトラブルによって遺産分割協議が中断したり難航すると、「遺産分割調停」や「遺産分割審判」という手続に移行します。この2つの手続きは一体どんな内容なのでしょうか。
遺産分割調停は、何らかの理由で遺産分割協議が成立しないとき、家庭裁判所を介して話し合いを進める方法です。
裁判所での手続ですが、裁判所が話し合いを仲介してくれるという手続なので、基本的には当事者の意見を尊重したものになります。家庭裁判所の調停委員会が争いのある相続人の間に入り、当事者同士が直接話し合わなくても協議が進むよう、取り持ってくれるというイメージでしょうか。
ちなみに、家庭裁判所の調停委員として選ばれるのは、弁護士や医師など、教養のある40歳以上の人とされています。
遺産分割調停では、調停委員という第三者を相手に主張をするので、遺産分割協議では出てこなかった話が明らかになることもあります。調停では、法律の専門家である弁護士に同席してもらい、法的に筋の通った主張になるようサポートしてもらうことも可能です。
遺産分割調停では、遺産分割調停申立書及び関連書類を準備する必要があります。具体的には以下の通りです。
また、遺産分割調停は通常、3か月から1年以上に及ぶことが多いです。平成27年の司法統計によれば、回数は「6回~10回」が25%、期間は「6か月~1年以内」が33%で最多でした。この結果を見ても、かなり手間のかかる手続きであることがわかります。
遺産分割審判は、遺産分割調停でも話し合いに決着がつかないとき、家庭裁判所が当事者の意見を踏まえて判断する手続です。こちらは調停(話合い)での解決ではなく、家庭裁判所の判断が示されることにより手続が終了します。
遺産分割審判は、主に以下のようなステップで進められます。
また、審判の内容に不服がある場合には、2週間以内であれば即時抗告という異議を申し立てることができます。ただし、既に主張したことの繰り返しに過ぎない場合は、抗告が認められず、棄却という結論が出されるので注意が必要です。
このステップを見てもわかるとおり、3でいかに証拠書類や資料をしっかり準備し、主張するかが重要になります。
調停・審判のいずれにおいても、法律の専門家による助言・サポートは必須です。遺産分割協議が不成立に終わったならば、すぐさま弁護士へ相談を持ち掛けましょう。例え調停で終わるとしても、家庭裁判所に同行・同席してもらえるため、法的な主張というサポートが受けられますよ。