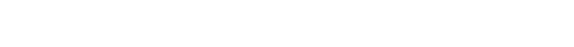
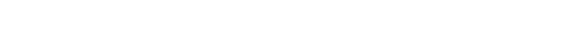
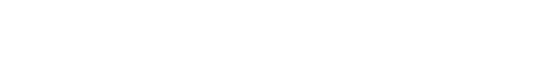

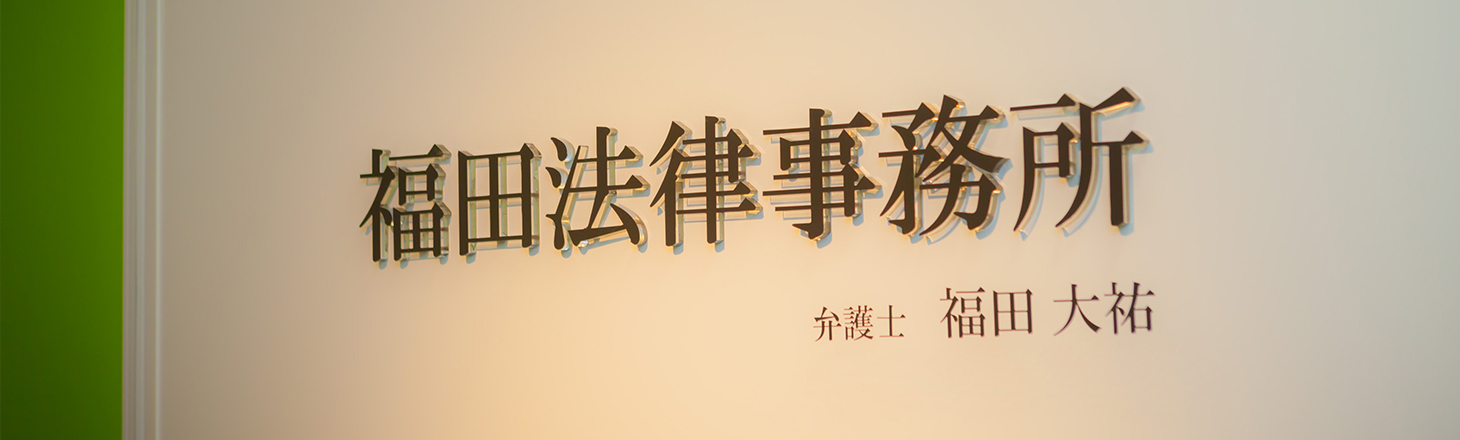
法定相続分は法律で一律に決められていますので、個別具体的な事情をみたときに、法定相続分で分割することがかえって不公平になることがありえます。
典型例は、複数いる兄弟のうちの1人が被相続人と長年同居し、被相続人の家業を手伝い、生活費を負担し、最後は介護に従事したといったケースです。
このようなケースでも、法定相続分は兄弟で均等ですので、法定相続分に従えばかえって不公平な遺産分割になってしまいます。
したがって民法は、このようなケースに備えて、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときには、寄与分という形で法定相続分を超える財産の取得を認めています。
寄与分が認められるためには、相続人の寄与が特別の寄与でなければなりません。例えば夫婦間、親子・兄弟間にはもともと扶助義務・同居義務が民法で定められているので、その範囲内の寄与であれば、特別の寄与とは認められません。
寄与分は、認められた相続人の遺産分配を厚くするものですので、寄与は被相続人の財産を維持・増加させるような貢献である必要があります。頻繁に会いに行き、よく被相続人の話相手になって感謝されたといった非財産的な貢献では寄与分は認められません。
寄与分は公平のための制度ですから、被相続人の財産の維持又は増加に貢献していても、その貢献に財産的な対価が支払われていれば、特別の寄与とは認められません。
寄与分は、まず自分以外の相続人との間の協議において主張します。寄与分を含めた遺産分割協議が整わないときは、家庭裁判所の遺産分割調停・審判で寄与分が決まります。
寄与分を主張する相続人が、遺産分割調停の中で寄与分の調停・審判の申し立てを行います。寄与分だけの調停・審判の申し立てはできず、必ず遺産分割調停の中で申し立てる必要があります。
調停・審判に関する記事一覧はこちら