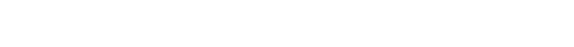
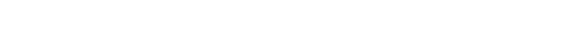
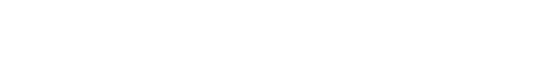

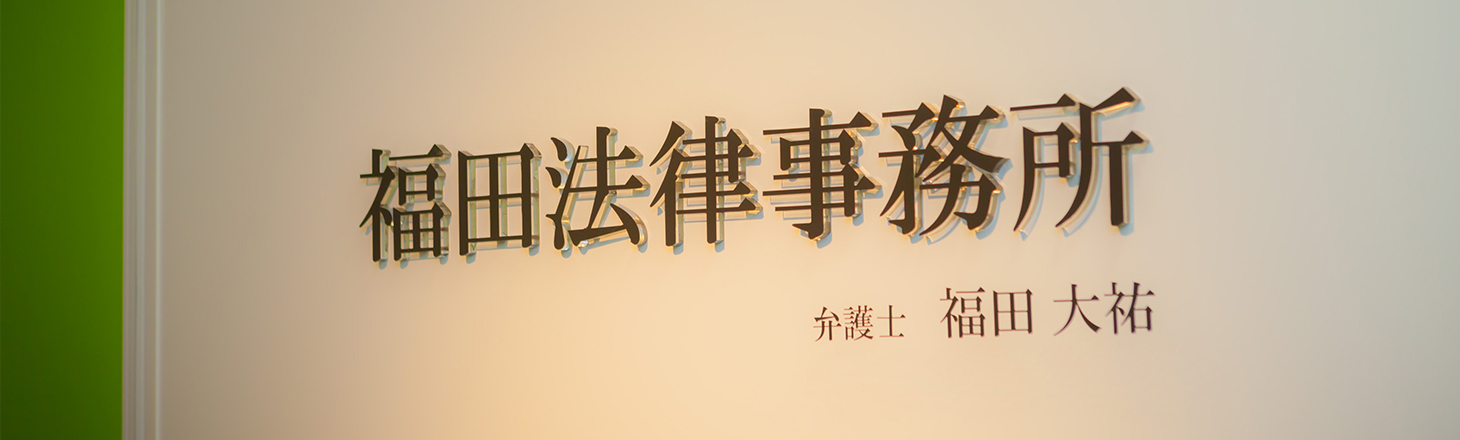
相続税という言葉はみなさん聞いたことがあるでしょう。
しかし、自分が相続人になったとき、相続税を支払わなくてはならないのかをきちんと把握している人は意外と少ないかもしれません。
相続税について学んでいきましょう。
亡くなった人から、各相続人等が、相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が、基礎控除額を超える場合には課税対象となります。
相続税がかかる財産というのは、相続や遺贈などの対象となる財産の他、
基礎控除額は、平成27年1月1日に相続税制度が改正されたことにより、
3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
となっています。
たとえば、相続人の人数が妻と子ども2人の合計3人であった場合、基礎控除額は3000万円+600万円×3=4800万円となり、4800万円を超える部分に相続税が課せられるのが基本となります。
被相続人が亡くなってから、相続税を申告するまでの大きな流れは以下のとおりです。
亡くなった方の財産をリストアップして遺産総額が基礎控除額を超えるかを計算し、相続税の申告が必要かを判断します。
なお、各種特例を受ける場合は、特例措置の適用により、たとえ申告する税額が0円になっても相続税の申告は必要となるので注意しましょう。
ここで税額軽減の例を1つ挙げると、配偶者に対する税額軽減の特例というのがあります。これは、配偶者が相続や遺贈によって実際に取得した財産の価額が1億6千万円以下である場合、又は課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を掛けた金額以下である場合には、相続税の計算上、配偶者には相続税がかからない仕組みのことをいいます。
等、これらの他にも多くの書類が必要となります。準備するものは、各特例措置の適用を受けるかによっても異なりますので、必ず事前に確認しましょう。
(2)で収集した資料をもとに、相続税の申告書を記載します。
相続税の申告書には第1表から第15表までの様式があります。相続税の申告書は第1表のみで、あとは計算書や明細書などの添付書類になるので、該当するものを提出することになります。
相続税の申告期間は相続人が相続を知った日(被相続人の死亡日であることが多いでしょう)の翌日から10か月間と定められています。期限内に申告しなければ、加算税や延滞税などが課される場合もありますので注意が必要です。
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長です。
相続人の住所地を所轄する税務署長ではありませんので注意が必要です。
相続税の申告書は、被相続人から相続した複数の相続人が共同で作成して提出できます。
しかし、共同申告ができない場合には、別々に申告書を提出しても差し支えありません。
相続税の申告には期間制限もあるうえ、多くの書類も収集しなくてはなりません。
また、そもそも他の相続人は誰なのかということや、遺言書があった場合の取り扱いなど法的な判断を要する点もあります。
書類記入に誤りがあった場合や見つかっていなかった財産が発見された場合には、税務調査がされることもあります。
確実かつ正確に相続税の支払をすることが重要となりますので、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
その他の記事はこちら
https://dev-souzoku.undo.jp/others/