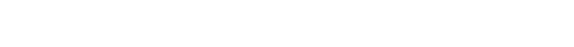
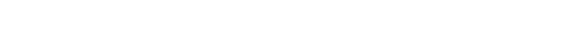
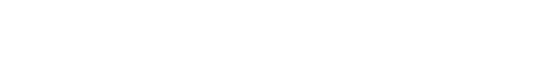

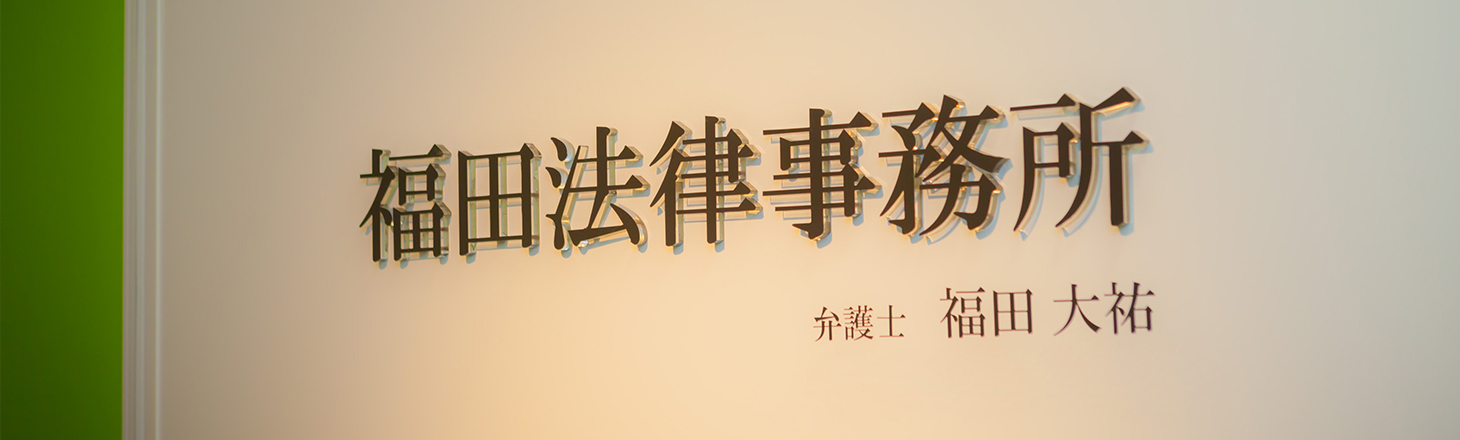
会社の代表取締役社長が突然亡くなってしまった。このような場合、どのような手続をとればよいでしょうか。
会社は個人(自然人)とは別個に存在を認められているので、代表取締役が亡くなっても会社までなくなったものとして取り扱われるわけではありません。
しかし、会社の登記簿には代表取締役が登記されていますし、代表取締役が亡くなれば会社を代表して経営する者がいなくなります。
そこで、会社の代表者である代表取締役が亡くなった場合には、新たな代表者を選ぶ必要があります。
なお、取締役会設置会社は取締役が3名以上必要です。
代表取締役が亡くなったことで取締役が3名未満になった場合には、取締役が3名以上になるように取締役を追加で選任しなくてはなりません。もし、取締役を補充できないのであれば、「取締役会の廃止」の手続きが必要です。
会社の規模が大きくなかったり家族で経営をしているような場合は、①②の手続などは比較的容易にできるでしょう。
新しい代表取締役が決まれば、亡くなった代表取締役の死亡による退任登記と同時に後任として選任された取締役(代表取締役)の就任登記をします。
亡くなった代表取締役が、会社の借入金について連帯保証人になっていることも少なくありません。
このような場合、代表取締役の相続人は、相続放棄をしない限り、借入金を引き継ぐことになります。
このような場合には、相続人から、新たに代表取締役になった者に対して、株式等の財産を渡す代わりに債務を引き受けてもらえないかなどの打診をすることも考えられます。
代表取締役が亡くなって、会社を存続させることができないような場合はどうすればいいでしょうか?
会社を解散させるか否かは、最終的には会社の株主が判断することです。そのため、会社を解散させるには株主総会によって解散決議をする必要があります。
代表取締役が亡くなった機会に会社をたたむという判断をする会社は、亡くなった代表者が全株式をもっている場合も多いと思われます。そのような場合は相続によって株主となる相続人が解散を決めて、清算手続をすることになります。
清算手続の具体的な流れは、
なお、債務が弁済できない状態で解散するには破産手続を取ることになります。
代表取締役が亡くなった場合に残された会社や家族がとるべき行動は、その会社に取締役が何人いるか、取締役会は設置されているのか、定款の規定はどうなっているのか、会社をどうしたいのか、株主は誰か……などによって大きく異なります。また、手続自体も煩雑で専門的知識が必要なものが多くあります。
代表取締役が亡くなって困った後継者や相続人はまず、専門家に相談することをお勧めします。
また、代表取締役は、自分が死亡したときにはどうするのか、終活の一環として、あらかじめ、専門家に相談して対策をしておくのがよいでしょう。