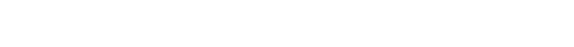
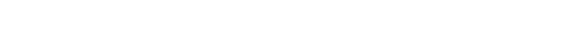
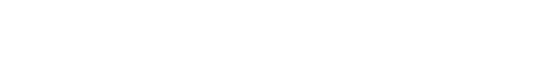


遺贈は、被相続人が遺言書を書くことで、相続人に相続財産を与える行為を指します。
通常の相続は相続人が相続財産を全て受け継ぎますが、遺贈は遺言書によって遺産の一部もしくは全部を無償か一部の負担を付与して相続人や相続人以外の人に受け継ぐことを意味するのです。
遺贈を受ける方は、受遺者と呼ばれています。
このように書くととても難しいように感じるため、今回は遺贈の種類と効力や特定遺贈について、遺贈を放棄することは可能なのか、特定遺贈のメリットとデメリットについてご紹介します。
目次
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
まずは、この2つがどのようなものか、効力はいつ発生するのかといった点について見ていきましょう。
包括遺贈は、「財産の半分を〇〇さんに遺贈する」といったように、財産の全部もしくは一部の割合を指定して行います。
包括遺贈の場合は、相続人と同じ権利義務を負うことになるため、もしも借金のようなマイナス財産があるとそれも引き受けなければいけません。
つまり、場合によっては受遺者にとってデメリットになってしまう可能性もあります。
特定遺贈は、具体的に遺贈する財産を指定するものです。
包括遺贈とは違って遺言で指定されていない場合、借金などのマイナス財産を引き継ぐことはありません。
遺贈は、遺言によって行われます。
遺言は、遺言者が死亡した段階から効力が生じると民法985条1項で定められています。
遺贈も同じタイミングで効力が生まれ、受遺者に承継されるのです。
つまり、遺言者が死亡しなければ効力は発揮しないということになります。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈がありますが、当記事では特定遺贈について詳しく解説していきます。
では、特定遺贈がどのようなものなのか深堀していきましょう。
特定遺贈は、遺言者が特定の財産を指定し、指定した人に遺贈します。
ここで重要になるのは、どの遺産が遺贈の対象なのか具体的に特定できるようになっている状態でなければならないことです。
銀行預金の場合は、金融機関名や支店名、預金の区別(普通、定期、当座など)、口座番号などをきちんと明記しておく必要があります。
不動産の場合は、不動産登記上の記載の通りに明記する必要があります。
登記上の所在地の書き方は普段の住所表記とは異なるケースが多いため、間違えないようにしましょう。
また、建物は屋号番号など普段は振れることがない表記も必要になるので、登記を取り寄せて確認しなければいけません。
受遺者が遺贈を放棄すると、放棄された財産は遺産の一部と見なされ、相続人の分割遺産の対象になります。
つまり、相続人は受遺者が受け取るかどうかによって受け取れる遺産の範囲が変わるのです。
しかし、受遺者が放棄の意思を表示する際の期間の制限は設けられていないため、好きなタイミングで放棄することができます。
そうなってしまうと、相続人はどこまで遺産を分割すればいいのか分からなくなってしまい、トラブルの種になってしまう可能性も考えられるでしょう。
トラブルを回避したり、不安定な状態を継続させたりしないために、一定の利害関係を持つ相続人は受遺者に対して遺贈を承認するか放棄するか決めてほしいということを催告できるようになっています。
催告を行った場合、受遺者は催告された期間内に承認か放棄の意思を示さなければいけません。
意思を示さないと遺贈を承認したとみなされます。
そして、それ以降遺贈の放棄ができなくなるため、遺産の範囲が明確になるのです。
結論から言ってしまうと、遺贈は放棄することができます。
遺産を放棄することになるため、相続放棄と遺贈放棄の違いがいまいちわからないという人もいるでしょう。
そこで続いては、相続放棄と遺贈放棄の違いや遺贈放棄の方法についてご紹介します。
相続放棄は、相続によって取得する予定に財産を放棄することです。
それに対して遺贈放棄は、遺言で取得することが定められた財産を受遺者が放棄することを意味します。
つまり、放棄する財産が相続にとって取得されたものなのか、遺贈によって取得されたものなのかによって変わるということです。
特定遺贈を放棄したいと考えている場合は、遺言執行者や他の相続人に放棄する旨を伝えるだけで済みます。
口頭で伝えるだけでも良いとされていますが、後からトラブルにならないようにするためにも、内容証明郵便などで知らせた方が良いでしょう。
包括増位の場合は、相続放棄と同じように家庭裁判所に申述をしなければいけないという点が相違点になります。
最後に、特定遺贈ならではのメリットとデメリットについて見ていきましょう。
メリットには、借金を引き継がないというものがあります。
包括遺贈の場合は、借金もひきついでしまうため、マイナスになってしまう可能性も考えられます。
それに対して特定遺贈の場合は借金を引き継がないので、マイナス財産を引き継がなくていいという安心感を得られるでしょう。
デメリットには、遺言書を作成した時と相続が発生した時で財産の状況に変化があった場合、問題になる可能性があるといったものが挙げられます。
遺言書を書いた段階で市場価格が5,000万円の土地①を相続人のAさんに、同じく市場価格が5,000万円の土地②をBさんに分けようと考えていたとします。
その段階では公平に分けられていますが、相続が発生した時にどちらかの土地が値上がりし、もう片方が値下がりしているというケースも考えられるでしょう。
そうなってしまうとトラブルに発展する可能性が高くなります。
特定遺贈によって、具体的に遺贈する財産を決めることができます。
また、マイナス財産を引き継ぐこともないので、受遺者にとってのメリットは大きいと言えるでしょう。
しかし、遺贈に関する正しい知識を持っている人は少ないため、遺贈を検討するのであれば遺産相続などに関する実績を持つ弁護士に相談するのがおすすめです。
適切なアドバイスをしてもらうことができるため、トラブルの回避にもつながります。
このコラムの監修者

福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。