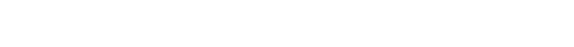
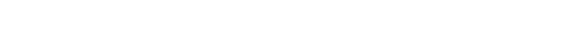
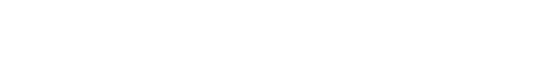


2019年7月に相続法は1980年以来、約40年ぶりに大きく見直されました。
改正の背景は、国民の平均寿命が延びて高齢化社会が発展するなど社会経済が大きく変化したことから、その変化に対応するためです。
相続法改正に伴い、相続人が最低限受け取れる財産範囲を示す遺留分制度も見直されています。
具体的に今までの遺留分制度と何が変わったのでしょうか?
今回は相続法の改正で遺留分制度の変更点や改正によるメリットなどについて解説します。
目次
今まで、相続の清算で遺留分を侵害された場合、相続人は「遺留分減殺請求権」を申請することで最低限の相続財産を確保できました。
今回の改正により「遺留分侵害額請求権」に変更され、金銭債権として扱われるようになったのです。
以前の制度では、目的の達成に物権的な効力により相続財産を構成する現物の持分を取得していました。
しかし、遺留分権利者の持ち分を清算する目的を果たすために、物権的効力まで認める必要はなく、侵害された分に匹敵するお金が支払えば済むのではと指摘を受けていました。
つまり改正後は現物の持分から最低限の財産を確保するのではなく、遺留分の侵害額に相当する金銭の請求が可能となったのです。
遺留分制度が改正されたことで、相続に関する様々な問題点が解消される可能性があります。
具体的に解消が期待される問題点は次の5つです。
以前の制度では、遺留分の侵害を申し立てられると全ての財産が相続人で共有状態となり、すぐに分けられなくなっていました。
不動産のような分割が難しい現物もあるので、共有状態の財産を分割するために共有物分割訴訟に発展することもあります。
さらに、未分割の株式は準共有状態となってしまうため、株式の議決権の行使できないとい問題点も生じます。
しかし、改正後は金銭での請求となるので共有物分割訴訟は起きなくなると期待されています。
遺留分を得るためには、他の相続人に遺留分の侵害額を支払うように請求が必要です。
その際、基礎財産の算定が必要です。
以前は生前贈与されたものに期限がなく、基礎財産の算定に含まれていました。
そうなると、相続人に生前贈与があっても無意味だと危惧されていたのです。
今回の改正により生前贈与が基礎財産に含まれるものは、10年以内のものと定められました。
それにより、10年より前の生前贈与は基礎財産に含まれずに済むので、遺留分の権利者にとっては不利ですが、遺留分の請求側にとっては有利になる可能性があります。
以前は遺留分の侵害を請求されると相手から承諾がないと、遺言執行者は遺言執行を実行することができませんでした。
その理由は、遺留分の権利者の権利は遺言者の意思に優越していたからです。
しかし、改正で金銭債権化されたことで請求を意思表示されても、遺言執行者は問題なく遺言執行を行えるようになりました。
不相当な対価の有償行為とは、時価よりも安い価格で財産を譲渡する行為です。
例えば、時価4500万円相当の不動産を1000万円で譲渡するといった行為が該当します。
このケースだと、1000万円支払って不動産を譲り受けたので、実質は3500万円の贈与となり、相続財産が減ってしまうことになります。
以前のルールでも差額分の遺留分も請求対象でした。
しかし、請求の際に譲り受けた不動産の時価が遺留分の算定基礎財産に含まれるため、遺留分の権利者は不相当な対価の1000万円を支払う(償還する)必要があったのです。
ところが、今回の改正で償還が不要となったので、直接減殺を実行できるように変更されました。
改正により新しく相続債務の弁済による控除が設けられました。
遺留分の請求を受けた側が被相続人の借金を返済していた場合、相続人が財産を引き継ぐ際に弁済された分の負担は免れ、公平性に欠けるとされていました。
そのため、遺留分の請求があった時は弁済でなくなった分の債務分は遺留分請求額から控除できるようになったのです。
遺言書により相続が実行された場合、できれば遺留分を侵害しないように被相続人が配慮して作成する必要があります。
しかし、様々な事情から遺留分の侵害を受けてしまう相続人がいます。
遺留分の請求を受けた側は、法改正により現物ではなく金銭で解決しなければなりません。
そのため、請求された金額に相当する金銭の確保が求められます。
そこで原資として備えておくと良いものが生命保険金です。
生命保険金は受取人の固有財産に相当するため、原則遺留分の算定基礎財産の対象にはなりません。
また、受取人が独自で生命保険金の請求ができるので、請求を受けた際に速やかに対応できるという点もメリットになります。
相続法の改正で遺留分の侵害を請求する場合、遺贈や贈与を受けた当てに侵害額に匹敵する金銭の請求が可能となりました。
不動産や株式など財産が共有状態になることを回避できたり、10年以上前の生前贈与は算定基礎財産に含まれなくなったりなど、公平性が高まったと考えられます。
それでも遺留分の問題は複雑なので、トラブルは相続に詳しい専門家への相談がおすすめです。
このコラムの監修者

福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。