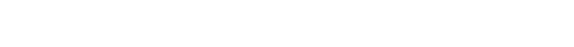
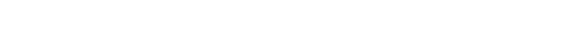
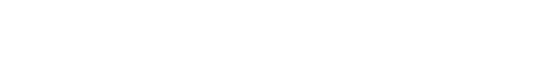


相続において、亡くなった人の預貯金がそのまま相続人の口座に振り込まれるわけではなく、そこまでの過程で葬儀費用や相続税の納付など、数々の出費が発生します。
そこで気になるのは、葬儀費用や財産の管理費など、相続が終了するまでの過程でかかった費用は控除の対象となるのかということではないでしょうか。ここでは、相続する際にかかった費用を控除できるかどうかについてご紹介します。
相続財産にかかる相続税は、手元に残る遺産の金額が少なくなれば、それだけ節税にもつながります。今回のように、課税対象となる財産から控除することを法律上、「債務控除」といいますが、この債務控除できる項目について、相続税法では次のように定められています。
相続は、人の死亡によって開始します(民法882条)。つまり、相続が開始した(被相続人が死亡した)時点で金額が確定していること、尚且つ被相続人の債務であれば、控除の対象になります。
しかし、相続開始から終了までの間に不動産の管理費用、遺言執行料、戸籍謄本代などもかかります。これらの費用は被相続人の死亡時に金額が未確定な上に被相続人本人の債務ではないことから、残念ながら控除の対象にはなりません。
では、「相続時に確定している被相続人の債務」とは具体的にどのようなものがあるでしょうか。
不動産や車などの各種ローン、金融機関や個人からの借入金
相続発生後、準確定申告で納付した固定資産税、社会保険料、所得税や地方税などが対象となります。延滞税が発生している場合、被相続人の責めに帰すべき理由で発生していれば控除されます。相続人の責めに帰すべき理由で円大全が発生した場合は控除されません。
相続人以外の人が被相続人に無償で労務を提供したことで、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与があった場合、相続人が特別寄与料を払えば債務控除の対象になります。
債務者本人が弁済すれば被相続人が代わりに弁済する必要がないため、原則として控除の対象にはなりません。ただし、債務者本人が弁済不能状態で、連帯保証人である被相続人が弁済後に債務者本人に求償しても、返還される見込みがない場合は控除できます。
慰謝料や損害賠償金など、発生することは確実でも金額が確定していない場合は控除されません。
被相続人の死亡によりローンを完済し、住宅を取得したことになるので控除されません。
いずれも被相続人の債務ではなく、相続人の家事費用から支出されるべきものであるため、控除の対象にはなりません。
相続税法では、債務控除の対象として「葬儀費用」と規定していますが、実際には葬儀にかかった費用全額が控除されるのではなく、一部の項目に限定されています。
上記は、あくまで社会通念上認められる範囲内で控除の対象となります。控除されないものは次の通りです。
葬儀の参列者からいただいた香典は、「香典返し」としてその半額程度の金額のものを渡します。香典は喪主に対する贈与であり被相続人の財産ではないため、香典返しの費用は控除の対象外となります。
墓地や仏壇、神棚といった祭祀財産は故人を弔うために必要なものですが、葬儀には直接関係がないため、控除の対象にはなりません。
初七日や四十九日は葬儀とは別の法事にあたるため、控除されません。ただし、最近では初七日を葬儀と一緒に執り行うことが増えたので、その場合は葬儀費用の一部として控除の対象となります。
基本的には被相続人が本来支払うはずだった債務についてのみ、相続財産から控除できます。ただ、被相続人の債務も葬儀費用も、上記に挙げた出費のほかにさまざまな費用が発生するかもしれません。
「これは控除の対象になるのか」と判断がつかないものが出てくる可能性も十分にあります。その場合は、相続に精通している弁護士に相談のうえ、相続手続きを進めるとよいでしょう。
このコラムの監修者

福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。