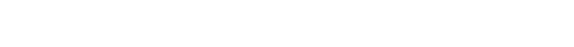
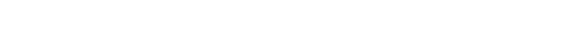
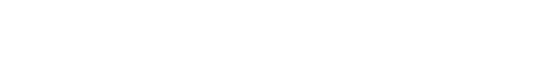


葬儀費用はある日突然、多額の費用が発生します。残された家族が高額な葬儀費用を用意できず、被相続人の口座から引き出すしかないときはどうすればいいでしょうか。
金融機関は口座を保有している人が亡くなったことを知ると、口座を凍結します。第三者が勝手に引き出してトラブルになるのを防ぐためです。ですが、口座が凍結されても必要な手続きを経てお金を引き出すことができます。ここでは、葬儀費用の捻出する方法と、被相続人の口座からお金をおろす手続きについてご紹介します。
目次
金融機関は、新聞または遺族からの連絡を受けて口座名義人が亡くなったことを把握できます。名義人が死亡した病院や死亡届を受理した自治体から金融機関に連絡することはありません。
つまり、新聞に掲載されなければ、家族からの自己申告でしか知ることができないので、銀行に死亡の事実を知られる前に口座からお金を引き出せます。ちなみに、特定の金融機関に名義人が死亡した事実を伝えても、他の金融機関には知らされません。
だからと言って個人の判断で勝手にお金を引き出すのは避けるべきでしょう。他の相続人から、「葬儀費用以外のお金も引き出しているのではないか」「他の口座も勝手に引き出しているのではないか」と疑いの目で見られてトラブルになるおそれがあるためです。被相続人の口座からお金を引き出す際には必ず他の相続人に伝えることが大切です。
また、葬儀費用という名目で引き出しているので、葬儀にかかった費用が一目でわかるように領収証や明細などを保管していきます。
相続放棄は、被相続人の債務を含む財産の相続を一切放棄することです。財産よりも借金の方が高額の場合に利用されます。
では、相続放棄を希望する相続人が葬儀費用を被相続人の口座から引き出すことは可能でしょうか。法律上、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合には、「単純承認」といい、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続したものとされています。そのため、相続放棄をしたい人は被相続人の口座からお金を引き出してはいけないと考えるかもしれません。
これに関しては意見が分かれるところですが、故人の身分相応な葬儀費用に充てているのなら問題ないとされています。反対に、生前の故人にとっては身分不相応で華美な葬儀を行った場合、その葬儀費用を含めて単純承認したとみなされるおそれがあるので注意しましょう。
2019年7月から遺産分割前の預貯金払戻し制度が創設されました。これにより、凍結された口座から預貯金を引き出すことができるようになりました。
払い戻しは、次のいずれかの方法でできます。
遺産分割の審判や調停で遺産に手を付けることはできない人が、生活の支弁等の事情により相続預金の仮払いの必要性があるとき、他の相続人の利益を害しない場合に限り、家庭裁判所が認めた金額を払い戻しできます。必要な書類は下記のとおりです。
家庭裁判所の判断を得ずに払い戻しをする方法です。口座を保有する金融機関で、最大で150万円までを払い戻しできます。必要書類は次の通りです。
なお、払い戻された預貯金について当該相続人が遺産の一部を遺産分割により取得したものとされます。つまり、当該相続人が本来相続する金額を超過する場合、超過部分は遺産分割時に清算することが求められます。
また、①は遺産相続をめぐって係争中であることが条件のため、葬儀費用捻出を希望される方は②の方法で払い戻すことになります。詳しくは被相続人が口座を保有する金融機関に直接お問い合わせください。
このように、葬儀費用捻出のために被相続人の口座からお金をおろすことは可能ですが、必要な手続きを経なければなりません。葬儀の前ということは、遺族は葬儀に向けて慌ただしく準備をしなければならないタイミングでもあります。省ける手続きはできるだけ省きたいと考えるはずです。
そこで、被相続人の口座からお金をおろさずに葬儀費用を捻出する方法として次の3つが考えられます。
被相続人が亡くなる前なら、上記の遺産分割前の払い戻し制度を利用することなくお金をおろせます。ただし、費用が高額であるため盗難にあわないよう保管場所には注意しましょう。
被相続人の死後、相続人の資力で葬儀費用をまかなえる場合は相続人が支払い、遺産分割時に清算する方法です。誰がどれくらいの金額を支出したのか記録しておく遺産分割協議の際に役に立つでしょう。
香典は法律上、贈与の一種であり相続財産には含まれないとされています。そのため、香典から葬儀費用を払うこともできます。どのくらいの金額の香典をもらえるか予想が難しい部分はありますが、葬儀費用の方が高額になった場合は超過部分を遺族が立て替えて遺産分割協議時に清算してもいいでしょう。
このコラムの監修者

福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。