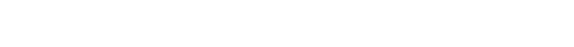
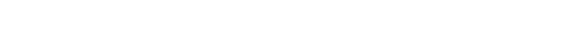
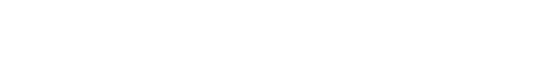


遺留分は、兄弟姉以外の法定相続人(配偶者もしくは子・直系尊属)に認められている、最低限の遺産の取り分です。また、意外と知られていませんが、遺留分は放棄することも可能です。では、被相続人がまだ生きている段階であっても、遺留分放棄は可能なのでしょうか。今回は、遺留分放棄の具体的な手続きや注意点など、生前の遺留分放棄を考えている方は必見の内容です。
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人について遺産の最低保証額を定めているという性質上、被相続人であっても奪うことができない権利です。しかし、被相続人が生きている間であっても、放棄することは可能です。ただし、無制限に放棄が認められるわけではありません。被相続人が生きている間は、決められた手続きを経たのち、遺留分放棄が認められます。
遺留分の放棄は、厳密にいうと「遺留分の請求、受け取りをしない」という意味になります。また、遺留分の放棄については民法の1043条に記載があります。
“第1043条 (遺留分の放棄)
1.相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
2.共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。”
この条文の1項をみてわかるとおり、遺留分の放棄には「家庭裁判所の許可」が必要です。具体的には以下のような手続きを行うことになります。
○生前の遺留分放棄に関する手続き
1.被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に「遺留分放棄の許可を求める審判」を申し立てる
所定の用紙に必要事項を記載し、家庭裁判所に提出します。ちなみに書式はこちらから参照できます。
(http://www.courts.go.jp/vcms_lf/21m-betsu1.pdf)
また、被相続人と申立人の戸籍謄本や、800円分の収入印紙、連絡用の郵便切手も必要です。
さらに、申立書には財産目録も記載する必要があるので、あらかじめ被相続人と協力しながら財産調査を済ませておきましょう。
2.家庭裁判所から審問期日が通知される
提出した申立書が受理されると、家庭裁判所から「審問期日」が通知されます。これはいわゆる「ヒアリングを受ける日」と考えてください。ちなみに遺留分放棄の審判では、
・本当に本人が希望して遺留分を放棄するのか
・遺留分を放棄する合理的な理由があるか
・遺留分を放棄する者に対し、被相続人から代償(贈与など)が払われているか
などが許可・不許可の判断基準になります。
3.遺留分放棄の許可・不許可通知がくる
審問が終わってしばらくすると、家庭裁判所から遺留分放棄の許可または不許可の通知が届きます。遺留分放棄が許可されたら、「遺留分放棄の許可証明書」を発行しておきましょう。相続手続きをスムーズに進めるために必須の書類です。ただし、遺留分放棄の許可はよほどの理由が無い限り撤回できません。後悔しないよう、しっかりと意思を固めてから望むようにしましょう。
被相続人の死後、つまり相続が開始されてから遺留分を放棄する場合は、生前よりも手続きが簡単です。
方法は2通りあり、ひとつは「他の相続人に遺留分放棄を伝える」、もうひとつは「遺留分減殺請求権の消滅を待つ」というものです。ちなみに遺留分減殺請求権は消滅時効が1年、除斥期間が10年です。
“第1042条 (減殺請求権の期間の制限)
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。”
「1年なのか10年なのかはっきりしない」と感じるかもしれませんね。要は「遺留分に関する権利を行使できると知ってから1年」もしくは「単純に相続開始から10年」ということです。つまり、被相続人が亡くなったあとに遺留分を放棄したいならば、基本的には1年間、何もしないでおけば良いことになります。
遺留分の放棄は、あくまでも「遺留分減殺請求権」を失う手続きにすぎません。遺留分を放棄しても引き続き相続には関係があり、遺産分割協議にも参加する必要があります。
そのため、「自分は相続に関わりたくないから」と安易な考えでの遺留分放棄はおすすめしません。もし、他の相続人との利害関係や遺産の調整を目的として遺留分放棄を考えているならば、必ず相続に強い弁護士に相談しましょう。特に、家庭裁判所への申立てや審判の手続きがある生前の遺留分放棄ならば、なおさらです。
このコラムの監修者

福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。