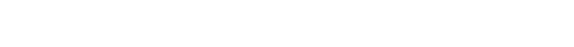
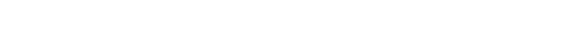
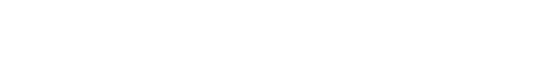


特定の人に財産を残したい、特にお孫さんに何か財産を残してあげたいときには、いくつかの手続きが必要です。なぜなら、何も手続きをしなければ、お孫さんは相続人にならないからです。
日本の民法では、遺産を受け取る人を「相続人」と呼び、この相続人になれるかどうかには序列のようなものがあります。そしてこの序列に従えば、孫は相続人になれないことが多いのです。
かわいい孫にどうしても財産を残したいとき、どのような方法があるのかを解説します。
目次
冒頭でも述べたように、お孫さんは相続人になれないことがあります。少し専門的ですが、民法887条・889条・890条を紐解くと、以下のように規定されていることがわかります。
“民法887条 (子及びその代襲者等の相続権)
1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。”
“民法889条 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2.第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。”
“民法890条 (配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。”
それぞれが何を規定しているか簡単に整理してみましょう。まず、民法889条は、「相続人の序列」を規定しています。
ごく簡単にいうと、1位が子ども、2位が両親、3位が兄弟姉妹です。また、民法890条では、配偶者が常に相続人になると規定しています。つまり、常に配偶者が相続人になり、その他は1位が子ども、2位が両親、3位が兄弟姉妹といった順序で相続人となるわけです。これを見ると「孫」が登場してこないことに気が付くと思います。
そこで民法887条を見てみましょう。ここでは相続人となるべき「子ども」が既に亡くなっているときや何らかの理由で相続権を失ったとき、さらにその子供つまり孫にあたる人物が代わりに相続権を受け継ぐと規定されています(これを代襲相続といいます。)。この「代襲相続」を行えば、お孫さんに財産を残すことができるわけです。
ただし、代襲相続は、その孫の親が相続人になれないというイレギュラーな事態に対応する方法です。そのため、被相続人(財産を遺したい人)が自分の意志でコントロールしにくいことも理解しておいてください。
自分が生きている間に、相続財産を先渡しする方法として「生前贈与」があります。
被相続人が誰にどれだけ渡すのかを自分でコントロールできるため、お孫さんに財産を残したい方にとっては手堅い方法といえます。
また、生前贈与は税金対策としても有効です。生前贈与のうち、毎月110万円まで贈与税が課税されません。
ただし,制度としては優れているのですが、他の相続人との不公平が生じないよう配慮が必要になるでしょう。お孫さんがトラブルに巻き込まれないよう注意したいところですね。
既に紹介した民法889条でも述べられているとおり、相続人の序列は「子ども」が1位です。そのため、お孫さんを養子縁組で子どもの順位につけておけば、財産を残すことができます。事前に「親と子」の関係を確定させて相続人の権利を与える、と考えてください。
ただし生前贈与と同じく、「いかにも」な方法にとらえられがちですから、他の相続人から反感を買ってトラブに発展しないよう注意が必要です。
遺言書へ明記することでも、お孫さんに財産を残すことができます。遺言は自筆(自筆証書遺言)でも構わないのですが、法的に有効な遺言書を作成しておきましょう。
また、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」を残しておけば、より確実かもしれません。公的な第三者が作成・管理を行うため、無効や偽造の心配がないからです。
さらに遺言の中で「遺言執行者(遺言の内容を実行する人)」を指定しておくと、相続がスムーズに進みやすくなります。遺言の内容はかなり自由に書いても認められることが多く、お孫さんへできるだけ多くの財産を残したい方なら是非検討すべきです。
簡単で手間もかかりませんが、やや不確実な方法です。生前にあらかじめ「遺産分割協議の中で孫へ遺産相続を検討してほしい」とお願いしておく方法です。
ただし、「言った・言わない」「聞いた・聞かない」になる可能性が高く、本当にお孫さんへ遺産が渡るかを本人が確認する手段がありません。
万全を期すならば、遺言書の中に「遺産分割協議で孫への遺産相続も取り上げること」などと明記しておく必要があります。
代襲相続を除けば、全て自分が生きている間に実行できる方法ばかりです。したがって、お孫さんに財産を残すのは決して難しいことではありません。
ただし、通常の遺産相続とはやや異なる手続きが必要で、そのすべてを自分で行うのは難しいでしょう。特に、生前贈与の方法や遺言書の作成方法などは、相続に強い弁護士のサポートを受けたいところです。強引に行えば、他の相続人の反感を買い、遺産を相続したお孫さんの立場が危うくなる可能性もあるからです。
確実かつ波風をたてず、できるだけ多くの財産をお孫さんに残したいならば、相続に強い弁護士への依頼を検討すべきでしょう。
このコラムの監修者

福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。