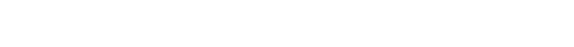
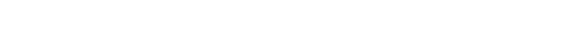
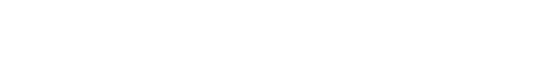


平成30年に民法(相続法)が改正され、遺産分割前に被相続人の預貯金の払い戻しができる制度が創設されました。それまでは口座名義人が死亡すると、銀行口座が凍結されていたのが、今後は必要な手続きを経ることで預貯金を払い戻せるようになります。この預貯金払戻し制度について詳しく解説します。
遺産分割前の預貯金払戻し制度は、亡くなった被相続人の預金口座から上限付きで口座からお金を引き出せる制度です。通常、口座名義人の死亡が判明すると、金融機関は当該名義人の口座を凍結し、遺産分割協議が終了するまで不正な引き出しがなされないようにします。
しかし、不正目的ではなく預貯金がどうしても必要となることがあります。それは、遺産分割協議が終了するまでの当面の生活費や葬儀費用などを預貯金から支弁したいといった事情があるときです。この制度が施行される前、被相続人の口座が凍結されているために、お金を引き出せないという問題が生じていました。
また、被相続人が生前に負担していた金銭債務があった場合、被相続人の死亡によって相続人が債務を相続したと判断されてしまい、弁済がないことを理由に財産を差し押さえられるなどの権利行使をされるおそれがあります。相続人がこうした不利益を受けないため、そして遺産分割を円滑に進めるためにも、容易に換価できる預貯金口座を払い戻すことで、早期に弁済することが望ましいと言えます。
そこで、遺産分割前の段階で被相続人の預貯金を払い戻しができる本制度が創設されたのです。金額の上限付きではありますが、必要な手続きをすれば預貯金を払い戻すことができます。
遺産分割前の預貯金を払戻しは、相続預金を持つ金融機関または家庭裁判所で手続きできます。それぞれの手続き方法についてご紹介します。
家庭裁判所の判断を経ず、金融機関に直接払い戻しを依頼できます。その際に必要なる書類は下記のとおりです。
その際の必要書類は次の通りです。
金融機関によって必要となる書類が異なる場合があるので、詳しくは預貯金口座のある金融機関に直接お問い合わせください。
なお、払い戻しできる金額は次のいずれかの金額になります。
(2)で、例えば被相続人の父親の預金残高が1200万円で相続人が妻、長男、次男の場合、法定相続分が4分の1である次男が単独で払い戻せる金額は
1200万円×1/3×1/4=100万円
という計算になります。この計算で150万円を超えた場合でも上限である(1)の150万円まで払い戻しを受けられます。
遺産分割の調停や審判を申し立てている場合に、家庭裁判所の判断によって預貯金の全部または一部を金融機関から払い戻しを受けられるようになります。金融機関とは異なり、払い戻し金額に上限はなく家庭裁判所が取得を認めた金額を払い戻してもらうことができます。ただし、払い戻すための条件が、下記の通り金融機関よりも厳しく設定されています。
必要となる書類は下記のとおりです。
相続人によって払い戻しされた預貯金は、払い戻しした共同相続人が遺産の一部を先に取得したものとみなされます。換言すれば「遺産の前払い」であり、遺産分割協議時には清算しなければなりません。
例えば、被相続人が父親、相続人が妻、長男、次男で、相続財産として1200万円の預貯金があったが、次男が預貯金払戻し制度を利用して100万円を引き出した場合、
ただ、次男は100万円を払い戻しているので、妻と長男は次男に対して代償金請求権100万円を取得しています。そのため、次男の法定相続分から100万円を控除し、その100万円を3人の相続人で法定相続分通りに分割します。
275万円-100万円=175万円
妻は100万円×1/2=50万円→相続財産の総額が550万円+50万円=600万円
長男は100万円×1/4=25万円→相続財産の総額は275万円+25万円=300万円
次男も100万円×1/4」=25万円を取得するので、275万円-100万円+25万円=300万円となり、法定相続分通りの相続できたことになります。
なお、払い戻した金額がその相続人の具体的相続分を超過する場合、当該共同相続人は超過した分も生産する義務を負うことになります。
このコラムの監修者

福田法律事務所
福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)
神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。